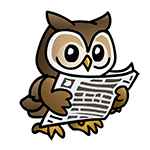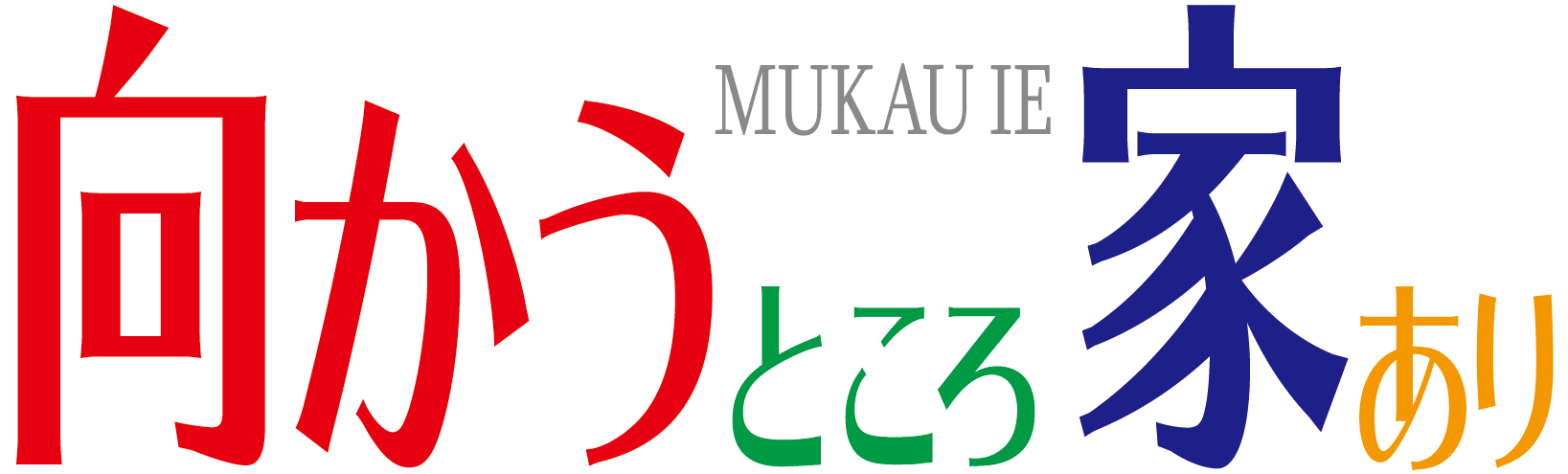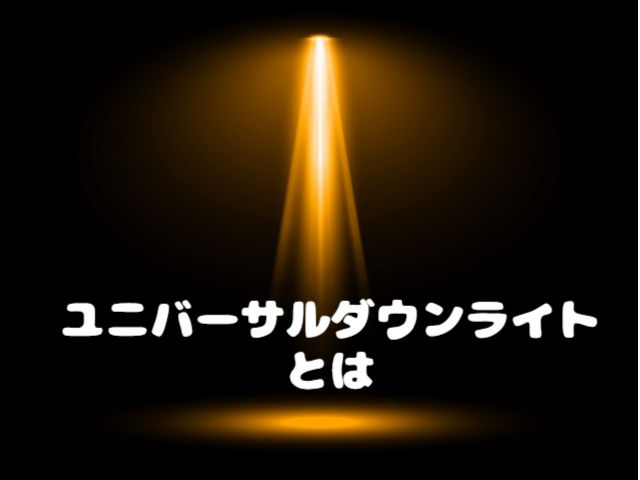LEDは長寿命なことで知られていますが、本当にそうなのか気になったことはありませんか?
LEDダウンライトは10年取り換え不要と言われていますが、2,3年で切れたっという噂も耳にします。
原因を知るには、まず仕組みからっということで、LEDが長寿命な理由や、故障の原因を探ります。
また、LEDダウンライトを設置するときに理解しておきたい種類(形)と、どういった場所に活用するのかをご紹介。
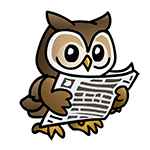

家づくりの取り組み
ダウンライトの光源は2種類
- LEDダウンライト(電球交換型)
- LED一体型ダウンライト
ダウンライトはLED電球なので長寿命で、省エネです。
照明器具は光を発する時に熱を持ちますが、LED電球は熱を発しない仕組みで光を放っています。
LEDってそもそも何?
「Light Emitting Diode」という英語の略で、発光ダイオードの事です。
※発光ダイオードとは電流を流すと発光する半導体(※)の事
(※)半導体とは、物質には電気を通す「導体」と、電気を通さない「絶縁体」がありますが、その中間です。人間が与えた条件によっては、電気を通したり、電気を通さなかったりします。
「導体」・・・金属(アルミニウムや銅)
「絶縁体」・・・ゴムやガラスなど
LEDが省エネで長寿命なのは
LEDが長寿命な事は世間一般的には知られていることですが、光を発する照明器具の中どうして、長寿命なのでしょうか?
それは、「光る仕組みの違い」によるものです。
白熱電球はフィラメントを熱することで光を発生させる
白熱電球の光る仕組みはフィラメントと呼ばれる細い金属線を熱することによって発生させています。
光る仕組みは電子がフィラメントの中を高速で移行することで生まれた摩擦(電気抵抗)です。
そのため、白熱電球は摩擦により熱を発し、2000℃以上の高温になります。
可視光の放射(人が見える光の波長の電磁波)に使用される電力はおよそ10%程度で、残りはほとんどが赤外線、摩擦による熱として消費されています。(※製品による違いあり。)
熱の発生にエネルギーを消費してしまうため、非常に無駄が多い仕組みとなっています。
また、スイッチのON/OFFを繰り返すと寿命が大幅に短くなります。
電流を流すとフィラメントに負荷がかかるので使用すれば使用すほど消耗され、切れると使えなくなります。

蛍光灯は電子が蛍光管に衝突し光が見えるようになる
蛍光灯は蛍光管の両極端にフィラメントがあります。
フィラメントを熱することで電子を反対側のフィラメントにぶつけます。
これが、蛍光管の中の水銀ガスとぶつかり合い、その反動で紫外線が発生します。
紫外線は目には見えないものですが、蛍光管に塗られた塗料にぶつかり、見える波長の電波に変換するという仕組みになっています。
可視光の放射(人が見える光の波長の電磁波)に使用される電力はおよそ20%程度で、残りは赤外線、紫外線、熱として消費されています。(※製品による違いあり。)
白熱電球よりは無駄がない仕組みです。
これも白熱電球同様、フィラメントに負荷がかかるので、使えば使うほど消耗し、フィラメントが切れると使えなくなります。
LEDは電子が孔子という穴に落ち込む衝撃で光る
LEDは白熱電球や蛍光灯のようにフィラメントがありません。
発光原理は蛍光灯と似ています。
蛍光灯やLEDは電子に過剰なエネルギーを与え、エネルギーが放出される原理をとっていますが、LEDは過剰にエネルギーを与える工程が違っています。
LEDはp型とn型という2種類の半導体を接合して作られています。
電流を流すとマイナス極側のn型にのった電子がp型の方向へ流れ、プラス極のp型にある正孔という穴に電子がぶつかり、結合します。
電子がもっているエネルギーを、正孔という穴からそのまま放出し、光が放たれるので、非常に効率が良い発光の仕組みとなっています。
要するに、電流が流れるとプラスとマイナスがくっつき、電子が持っているエネルギーを穴から放出させるという事です。
可視光の放射(人が見える光の波長の電磁波)に使用される電力は30~50%と言われています。(※製品による違いあり。)
光に変換されななかったエネルギーは熱に変換されますが、白熱電球や蛍光灯のように紫外線や赤外線が出ないのもLEDの良い所です。
LEDの光には、赤外線がほとんど含まれないため、熱さを感じることはありません。
しかし、LEDの電源部分や本体は発熱します。
LEDは熱に弱いという特性があるので、構造上は熱を上手く逃がしていますが、長期間使用していると放熱部分(フィン)の不具合や、機器の経年劣化でLEDの寿命が決まります。
LEDはフィラメントのような消耗品がないため、長寿命ですが、LED以外の機械的部分の耐用年数がおよそ10年です。
10年経たないうちにLEDダウンライトが切れてしまう原因はLED自体の問題ではなく、本体の劣化や接合部分の不具合によるものです。

LEDのまとめ
従来の白熱電球や蛍光灯は摩擦や過剰な電子の衝突で光を発生させていましたが、LEDは半導体が直接光に変換しているので、少ない消費電力で発光します。
光自体の発熱量は少ないし、長時間使っても熱くなりません。
不可視光線(赤外線や紫外線)が出ないので、身体にも優しい光源だと言えます。
また、フィラメントなどの消耗品を使用していないので、長寿命です。
10年間は寿命があると考えられるが、施工の不具合や機器の状態によっては寿命が短い場合もある。
っという事です。

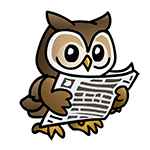
交換型のダウンライトの特徴(LEDダウンライト)
交換型のダウンライトは、白熱電球と同じ要領で電球を交換するタイプです。
照明器具本体は一体型のダウンライトと比べると少々高めですが、交換費用は電球だけで良いので、のちのちのコストがかかりません。

一体型のダウンライトの特徴(LED一体型ダウンライト)
一体型のダウンライトは交換型のダウンライトより安価です。
交換は電球と本体が一緒になっているため、まるごと交換します。
一体型のダウンライトの交換には、電気配線をつなぎ直す必要があるため、電気工事士の資格が必要になります。
自分では交換ができないため、交換費用がかかります。
1個交換するのにかかる費用は業者や交換するダウンライトの種類によって違い、1万円くらいはかかることは覚悟しておいた方が良いです。
ダウンライトが切れるタイミングはダウンライトごとに違うので、あちこちにダウンライトを取り付けている場合は交換を頼むタイミングが難しいです。
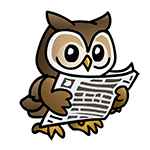

その間、耐えることになるのか。
なかなか不便。
一体型と交換型、どっちが安く済む?
現在はLED一体型のダウンライトが主流です。
なぜかと言うと、LED照明は長寿命で、10年間は交換不要とされているせいです。
一見、電球交換型のダウンライトの方が、交換費用を抑えられるため、初期費用がかかったとしても、トータル的に見れば安く済みます。
しかし、10年も経てば、消費電力の効率が悪くなる他、照明本体や電源ユニット、配線関係の劣化が心配され、故障の原因にもつながるので、どのみち、照明器具を丸ごと取り換えた方が効率が良いからです。

ダウンライトの種類(形別による機能)
- ベースタイプ(一般的な照明に)
- ユニバーサルタイプ(角度調節可能)
- ピンホールタイプ(上から真下を照らす)
大きく分けると3種類あります。
この他にも傾斜天井タイプ、軒下タイプ、防湿タイプがあります。
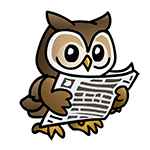

ベースタイプ(一般的な照明に)
一般的なダウンライトです。
部屋のあらゆる場所に設置されます。
LEDダウンライトには光の出方が拡散タイプと集光タイプがあります。
拡散タイプは、光の広がりが大きいので、リビングなど広い範囲を照らしたいときに使用されます。
配灯の工夫次第でも照明具合に差をつけることができます。

集光タイプは光の広がりが少ない、スポットライトのような使い方です。
目立たせたいもの、空間のメリハリをつけたいときに使います。

ユニバーサルタイプ(角度調節可能)
光の向きを変えることができるタイプです。
角度を変えられるので、凹凸のある壁を照らすと、陰影ができ、立体感がより際立ちます。
より強調させたいものがある場合はユニバーサルタイプを使うと高級感ができます。
また、子供のデスクライトの代わりに活用するっという人もいます。
角度が調節できるので、ある程度光の当たり具合に融通がききます。

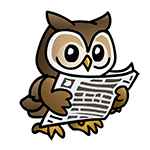
ピンホールタイプ(上から真下を照らす)

ピンホールタイプは照らしたいところにピンポイントで光を当てます。
画像のようなニッチ窓にピンホールタイプのダウンライトを使えば、さらにオブジェが際立ちます。
ユニバーサルタイプは角度が調節できますが、ピンホールタイプはできません。
周りを一切照らすことなく、真下を可能な限り照らしたい場合に使います。

機能的な空間するためにダウンライトを活用しよう
ダウンライトを上手く取り入れると、おしゃれな部屋や空間やお気に入りの場所になります。
大部分は、ベースタイプのダウンライトですが、ユニバーサルタイプやピンホールタイプも場所によって使い分けるとより機能的なお家、住宅になるのではないでしょうか?